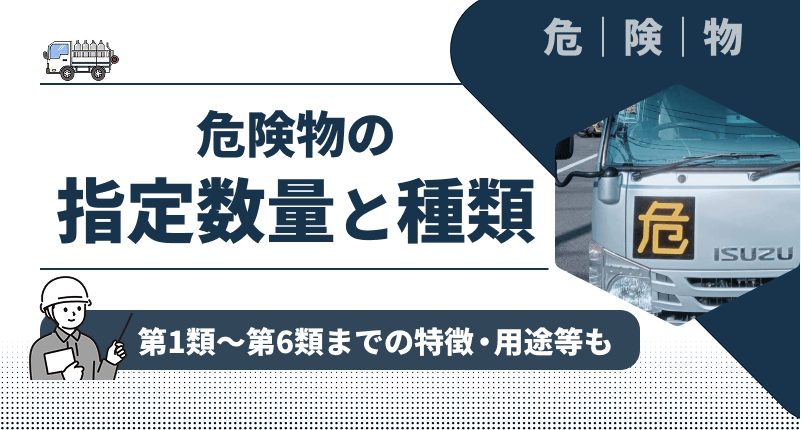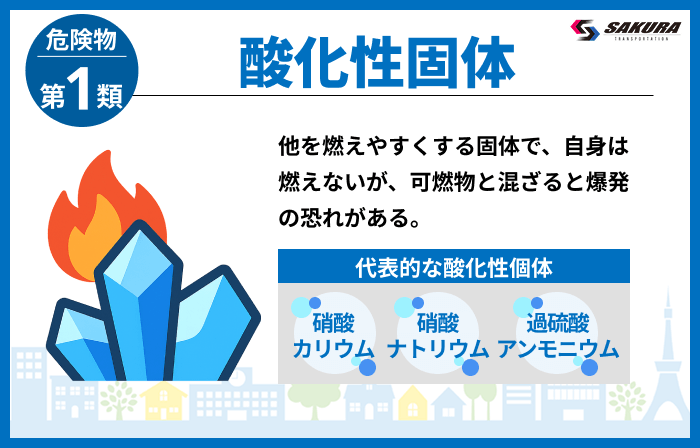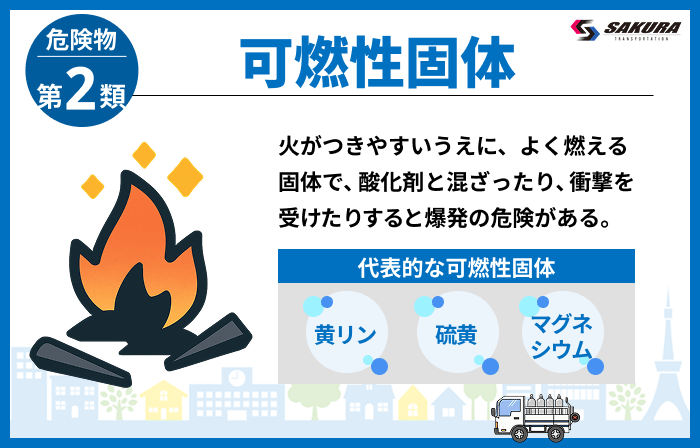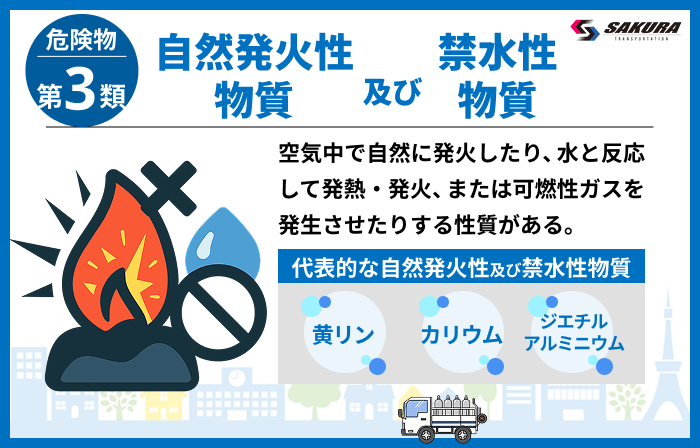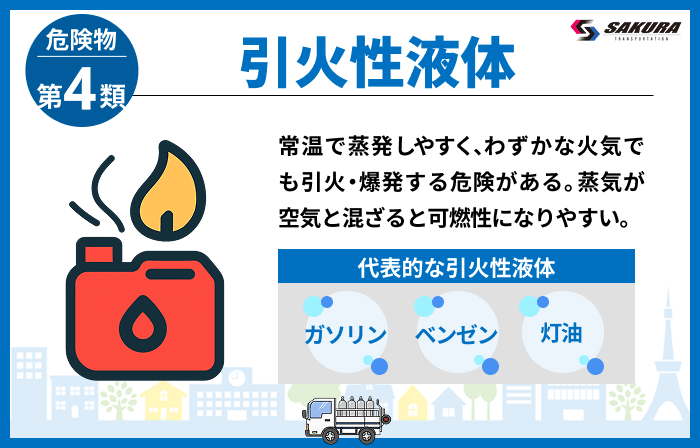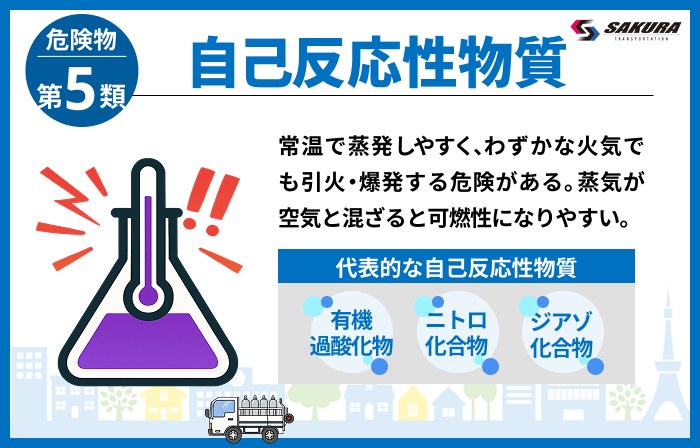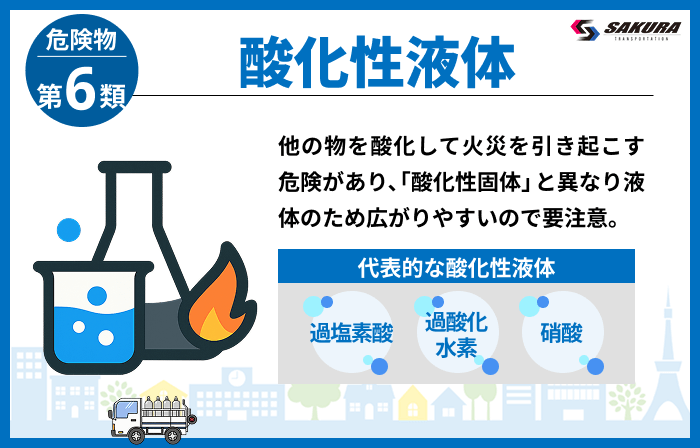危険物の指定数量とは、消防法第9条の3で
「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」と定義されている数量です。
これは、危険物の安全な取り扱いを目的として設けられた重要な基準で、一定量を超えると消防法に基づく厳しい規制が適用されます。
指定数量は、危険物の性質に応じて分類される以下の6種類に対して、それぞれ定められています。
危険物の種類
- 第1類:酸化性固体
- 第2類:可燃性固体
- 第3類:自然発火性物質・禁水性物質
- 第4類:引火性液体
- 第5類:自己反応性物質
- 第6類:酸化性液体
(参考)総務省消防庁|「危険物」とは?
(参考)消防法
(参考)危険物の規制に関する規則
(参考)危険物の規制に関する政令
1-1.第1種〜第6種の指定数量 一覧
各類の指定数量を、一覧形式でわかりやすくまとめました。
※もし以下の、指定数量を超えて危険物を貯蔵・取扱う場合には、消防法に基づいた厳格な規制が適用され、施設の届出や構造・設備に関する技術的な基準を満たす必要があります。
指定数量未満であれば、市町村の火災予防条例に基づき、比較的緩やかな規制のもとでの管理が可能です。
| 類別 | 品名・性質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 第1類 | 第1種酸化性固体 | 50kg |
| 第2種酸化性固体 | 300kg | |
| 第3種酸化性固体 | 1,000kg |
(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)
| 類別 | 品名・性質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 第2類 | 硫化りん | 100kg |
| 赤りん | 100kg | |
| 硫黄、第1種可燃性固体 | 100kg | |
| 鉄粉、第2種可燃性固体 | 500kg | |
| 引火性固体 | 1,000kg |
(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)
| 類別 | 品名・性質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 第3類 | カリウム | 10kg |
| ナトリウム | 10kg | |
| アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、第一種自然発火性物質および禁水性物質 | 10kg | |
| 黄りん | 20kg | |
| 第2種自然発火性物質および禁水性物質 | 50kg | |
| 第3種自然発火性物質および禁水性物質 | 300kg |
(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)
| 類別 | 品名・性質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 第4類 | 特殊引火物 | 50L |
| 第1石油類(非水溶性) | 200L | |
| 第1石油類(水溶性) | 400L | |
| アルコール類 | 400L | |
| 第2石油類(非水溶性) | 1,000L | |
| 第2石油類(水溶性) | 2,000L | |
| 第3石油類(非水溶性) | 2,000L | |
| 第3石油類(水溶性) | 4,000L | |
| 第4石油類 | 6,000L | |
| 動植物油類 | 10,000L |
(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)
| 類別 | 品名・性質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 第5類 | 第1種自己反応性物質 | 10kg |
| 第2種自己反応性物質 | 100kg |
(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)
| 類別 | 指定数量 |
|---|---|
| 第6類 | 300kg |
(参考)危険物の規制に関する政令|別表第三(第一条の十一関係)
1-2.危険物が2種類以上ある場合の考え方
消防法では危険物の「指定数量」を超えると規制対象になります。
ただし、複数の危険物を扱う場合は、それぞれの量を足すだけでは危険性を正しく判断できません。
そのため、各危険物の「指定数量に対する割合(=倍数)」を合計して判断します。
1-2-1.指定数量に対する割合の算出方法
「指定数量に対する割合」は以下の順序で算出します。
- 危険物ごとに「倍数」を計算
「倍数 = 実際の量 ÷ 指定数量」
- すべての倍数を合計
- 合計が1以上なら、消防法の規制対象になる
1-2-2.指定数量に対する割合のシミュレーション
例えば、以下の条件でシミュレーションを行ってみます。
- ガソリン:〈実際の量〉150L、〈指定数量〉200L
- 灯油:〈実際の量〉600L、〈指定数量〉1,000L
- 軽油:〈実際の量〉800L、〈指定数量〉1,000L
上記を「倍数 = 実際の量 ÷ 指定数量」の計算式に当てはめると、
- ガソリン:0.75
- 灯油:0.60
- 軽油:0.80
合計倍数:0.75 + 0.60 + 0.80 = 2.15
合計が1以上(2.15)のため、消防法による規制が必要になります。
(参考)大阪市|危険物規制について
(参考)鹿沼市|知って得する危険物